お金を貯める。その方法で真っ先に思いつくのが、ゆうちょ銀行・大手銀行・ネットバンクの口座へコツコツ入金することだと思います。
しかし、そのお金が様々な要因で目減りしていることをご存知でしょうか?
本記事では基本知識やデータを紹介しつつ、その理由と対策を見ていきます。
インフレーションについて
インフレーションの意味とその原因は?
インフレーションとは、物価が上がり、お金の価値が下がることです。略してインフレと呼ばれます。
原因は大きく2つ、「好景気」「コストの高騰」が挙げられます。
好景気
景気が良いと商品がよく売れて、需要が供給を上回り、物価が上がります。
これを、ディマンド・プル・インフレといいます。
コストの高騰
一方、賃金や原料の高騰などで、商品を作るためのコストが上がり、物価が上がることがあります。
これを、コスト・プッシュ・インフレといいます。
物価は年々上昇している
身近な食品の物価はここ20年でどれだけ変わっているのでしょうか?
いくつかの例を見てみましょう。
食料・飲料品
-1024x398.png)
2012年以降、じわじわと上がっていることが分かります。
ここで押さえていただきたいのは、グラフにはない食料品・飲料品にも影響があるということです。
なぜなら、小麦粉や食パンのみならず、これらを使う食品(例:サンドイッチや麺類)も値上がりすることにつながるからです。
公共インフラなど
-1024x423.png)
2016年以降にじわじわ上がっているのが分かります。
食料品・飲料品は「高いから買わない」ということができました。しかし、光熱費などは生活をする上でどうしてもかかるものです。
その料金の値上げが、家計を圧迫することは言うまでもありません。
消費者物価指数
物価を表す指標として消費者物価指数というものがあります。
消費者物価指数は、全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するものです。すなわち、ある時点の世帯の消費構造を基準に、これと同等のものを購入した場合に必要な費用がどのように変動したかを指数値で表しています。
このように、消費者物価指数は純粋な価格の変化を測定することを目的とするため、世帯の生活様式や嗜好の変化などに起因する購入商品の種類、品質又は数量の変化に伴う生活費の変動を測定するものではないことに留意する必要があります。
総務省統計局 消費者物価指数に関するQ&Aより
2000年から20年間の推移は以下の通りです。

2012年頃から継続的に上昇していることがわかります。
一方で、この指数は消費税を含めた価格を用いて作成されているため、増税の影響ではないかという指摘もありえます。
次に補足として、消費税の影響を調整した指数のグラフを紹介しておきます。
★補足★ 消費税調整済指数
これは、消費税率の改定による直接的な影響を除いた指数になります。
調整を行っているようですが、実際の課税処置に完全には適合していないとのことですので、あくまでも参考程度にしていただければと思います。

こちらを見ても、やはり2012年頃から上がっているようです。
- 1989年 消費税を導入 税率3%
- 1997年 税率5%に
- 2014年 税率8%に
- 2019年 税率10%に
エネルギー価格の値上げ
物価が上がる要因の1つとして、エネルギー価格の値上げが挙げられます。
円換算での原油価格(WTI)の推移を見てみましょう。

2020年のコロナショック以降、急騰していることが分かります。
これは、社会情勢と円安が大きな要因であると思われます。
West Texas Intermediateの略称。米国の代表的な原油。テキサス州西部を中心とした地域で産出され、硫黄分が少なくガソリンを多く抽出できる高品質な原油を指す。
野村證券 証券用語解説集より
ニューヨークマーカンタイル取引所において、その先物取引が行われており、原油価格の代表的な指標となっている。この先物取引を指すこともある。
食品のステルス値上げ
食品の値段が数年前と比べてあまり変わっていない印象を持っている方もいると思います。
しかし実際は、値段を据え置きつつ内容量が減少することで、消費者からは気づきにくい実質的な値上げをしています。
これをステルス値上げといいます。
「値上げ」と聞くとネガティブな印象を抱く方が多いと思います。
しかし、モノやサービスを消費することで、それは誰かの所得になります。
その所得によって消費が促進されれば好循環に繋がります。
「値上げ」自体が問題ではなく、物価の上昇に伴って給与が上がらないことが問題の本質だと考えます。
企業がステルス値上げを行わなければいけない理由
理由① 消費者離れを防ぐため
内容量をそのままにして、値段を上げると消費者は買わなくなってしまいます。
それよりは、少し量が減ったとしても前と同じ値段で手に入る方が消費者の心理的に受け入れやすいのではないでしょうか。
理由② 円安により、原材料費が高騰したため
企業は原材料をほとんど輸入に頼っています。
例えば同じ5ドルの材料を買う際、為替レートが1ドル100円であれば500円ですが、1ドル120円では600円かかります。
これにより材料費がかさみ、見込める利益が減ってしまいます。
他にも、商品の輸入の際に運搬で使われるのが船や飛行機で、これらは燃料で動いています。
円安による燃料の価格高騰が運搬コストとして企業に重くのしかかり、商品価格へ上乗せせざるを得なくなります。
また、原材料が国内のみであってもトラックの運搬にガソリンは必須ですので、やはり企業のコストに直結していると言えます。
理由③ 賃上げにつなげるため
企業は利益の中から従業員への給料を人件費として払っています。
その元となる利益が大きくならなければ、給与を上げることができないのです。
預貯金だけだとお金が減る理由
結論、預貯金だと金利が物価上昇率より低いからです。
近年、銀行は超低金利時代と言われており、2022年4月現在の大手銀行・ネット銀行の金利は年利0.001~0.2%です。
この数字は物価上昇率と比較すると低いといえます。
よって、増えるお金の量(金利) < 出ていくお金の量(物価上昇率)
となるため、実質的にお金が目減りします。
お金の目減りを防ぐ対策は?
お金を目減りさせないためには、物価上昇率以上に価値が上がるところにお金を置いておく必要があります。
例としては、現金を株式や金に変えるという方法が挙げられます。
しかし、預貯金には元本変動がなく、すぐに引き出せるという強力なメリットもあります。
また、株式は元本割れのリスクがあるため一概には言えないですが、ここでは資産分散の方法として捉えていただければと思います。
まとめ
- 物価は年々上昇しており、家計を圧迫している
- 円安や社会情勢の影響で商品の製造・運搬コストが上がっているのが物価上昇の理由
- 物価上昇が悪いのではなく、それと同時に給与が上がらないのが問題の本質
- 預貯金のみでは、増えるお金の量(金利) < 出ていくお金の量(物価上昇率)となり実質的に資産が目減りする
- 対策の1つは、現金以外(株式や金)の資産を保有する(投資する)こと
- 資産分散が重要で、「預貯金はダメ」ということではない
- 預貯金のメリットとデメリットを改めて認識しよう










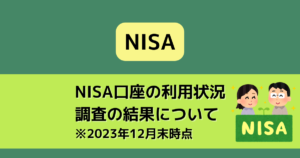
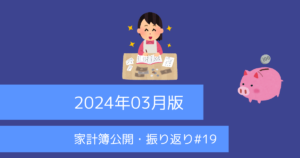
コメント